こんにちは。薬剤師のタコP🐙です。お薬のお話と40代からの子育てについて書いています。
今回は新社会人での印象に残る職場の先輩というタイトルにしました。社会人になって初めて勤めた職場で仕事をしていく上での心得などを丁寧に教えてくださった方について書いていきます。
はじめに
現在は薬学部は修業年限が6年間になり、学生の段階で薬剤師としての仕事をしていくための以下のような基本的な技術など私が卒業した時はその部分は不十分であったため、就職してから本格的に学ぶというのが現状でした。
- 処方箋を見て薬の量をはじめ、間違っている箇所はないか
- 粉薬や水薬を測り患者さんにお渡しできるようにするまでの準備をできるようにすること
- 患者さんにお渡しするロールプレイ
薬局の構造的な問題
さて、無事国家試験に合格し、薬局現場で働くことになりました。現在でもそうですが、調剤薬局では地理的に最も近いところにある病院や診療所の処方箋が持ち込まれる可能性が最も高くなります。そのため、薬を患者さんにお渡しする(=投薬と呼んでいます)にはどのような薬が扱われているのかと覚えておき、そして処方箋を見てこの人はどのような理由で病院にかかったのか、おおよその予測をたてられるようにならなければなりません。それにはある程度の経験が必要になります。初めて配属された薬局は薬剤師が8名在籍している薬局で総合病院の前にあり、あらゆる診療科の処方箋が舞い込んできます。しかし、この薬局は2階建てになっていて、2階に調剤室(薬を計量等してお渡しする準備をするところ)があり、1階はカウンターのみで、2階からエレベーターで降りてきた薬を1階で投薬するという珍しい構造になっていました。1階で投薬するということは基本的に自分自身で要領よく患者さんをさばいていくということであり、まだ経験のない私にとっては難問でした。このような少し特殊な薬局の構造のこともあり、まだ不安なところがたくさんありましたが、まだ一人前とはいえない私を指導してくださったのがIさん(当時40代男性)だったのでした。

仕事をしていく上での心得
IさんはNo.2の主任という立場でおられたのですが、私の指導係でした。通常新卒で就職した場合は研修期間として集団で研修所のようなところで仕事を教えてもらうということも多いと思いますが、薬局の業界は同じ会社でも店舗により運営方法が違うこともあり、現場で仕事をしながら教えてもらうことが多いようです。まず心得としておっしゃられたのが、「急いでいる時ほど冷静に、落ち着いて」というものでした。どんな仕事でもそうですが、忙しい時間があり、そのときはミスをしやすいものです。間違えずに仕事をしていくためには忙しくなってきて早く作業しなければいけなくても、気持ちは焦らず、順番に片づけていくことが必要になると思います。この心得は今も忙しくてパニックになりそうなときに思い出すようにしています。また、私が仕事に慣れてくると僕たちを仕事が遅いといじめないでねと言われました。もちろんそのつもりはなかったのですが、現在、私がほぼ当時のIさんの年齢になり、20代の後輩を見ると始めから一通り知識も作業もできる状態で就職してきていることに羨ましくも感じ、その気持ちがわかる気がするのです。
調剤薬局で働いていこうと改めて思ったきっかけ
一方、Iさんは趣味が剣道で、休憩時間になると竹刀のエア素振りをしていました。休憩時間にエア素振りをすることによって仕事と休憩の切り替えをしやすくしていたのかもしれません。また、若い頃はMR(=製薬会社の営業職)をしておられたらしく、その頃の話をよくしてくださいました。私はMRになるつもりは全くありませんでしたので、就職活動でもMRについて調べることはありませんでしたが、話を聞いているとMRはあくまで営業職なので、販売実績が最も問われるところになります。そのため、薬剤師の立場からすると本来必要ではない薬を半ば強引に売ったり、ライバル他社からシェアを奪うために他社製品を貶めたり、病院などの取引先を頻繁に接待するような営業手法も必要だったという話をされていました。私が就職した当時は薬学部卒業の男子は製薬会社でMRになるという学生もまだまだ多かったのですが、そのようなことを聞いていると私はMRにならなくてよかったと改めて思いました。
今から振り返ってみてもIさんに出会ったことはその後の私の人生の方向性を決めるうえで大きな要因となっていると思います。
皆さんの意見がありましたら、お問い合わせフォームからよろしくお願いいたします。

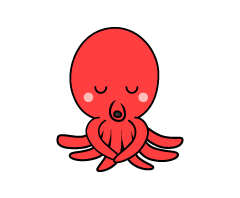
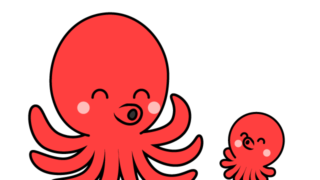
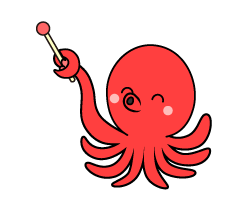




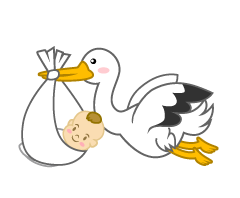

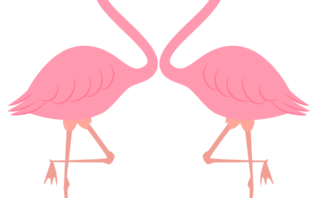



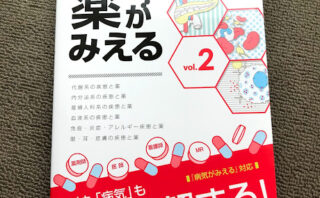






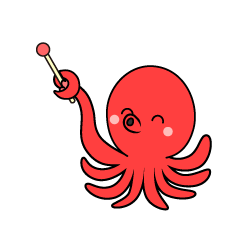
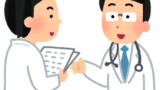


コメント