こんにちは。薬剤師のタコ🐙です。今回は保険の効かない薬について考えていきたいと思います。
先日のニュースから
先日27日に、NPO法人がノルレボという緊急避妊薬を処方箋なしでも薬局で購入できるようにしてほしいと厚労省に要望したそうです。この薬は72時間以内に1錠を服用すれば高確率で避妊ができるというものですが、処方箋なしで販売することに産婦人科の業界団体からは反対の意見が多数出ているそうです。理由としては直接患者さんが薬局に行くことになると薬剤師が服薬指導、副作用の説明をきちんとできるか?という理由のようです。
薬剤師の立場から思うこと
しかし、通常の処方箋調剤でもノルレボよりリスクが高く、副作用が出れば早い対応が必要な薬はたくさん扱っています。私が大学を卒業した時代は修業年限は4年でしたが、現在の薬学部は薬剤師養成課程は6年間になっていて、教えている内容もより実践に近い内容になっています。また、我々4年で卒業できた年代の薬剤師も新しい薬の情報はたえず仕入れるようにして、適切に患者さんに指導できるように努めています。確かに医師は患者さんに対して責任が重く、専門科目に関しては診断、治療に関してはスペシャリストであると思いますが、専門外になると薬の名前も知らないということはよく耳にします。薬剤師は多少得意、不得意はありますが、薬のことに関しては全般的に信頼してほしいなあと思います。そのために薬学部も修業年限が6年間になっているのでありますし、多額の税金が使われているので、医療資源と考えてほしいです。
立ち位置が微妙な薬たち
ところで、ほとんどの薬は薬価、すなわち国が決めた公定価格があり、薬の値段は日本中どこの病医院、処方箋調剤をしている薬局に行っても同じです。ただし、その人の自己負担割合(0~3割)、取っている手数料(=技術料と呼んでいます)によって違います。支払金額の違いはこの違いだけなのです。これについては別にお話します。しかし、ノルレボをはじめ、保険の効かない薬は薬価が決まっていません(=薬価未収載)。薬価がないので、その販売価格を自分で決めてよいのです。
私が考える薬価未収載薬が院内処方される理由
薬価のある薬は薬価改定と言って、少なくとも2年に1回は薬価が変わります。基本的に値段は下がっていく傾向にあります。ひと昔前までは薬価が高く、仕入れ値を安くできれば、病院で仕入れて高く売れるので、院内処方(=病医院の中で処方箋をもらわずに薬をもらう形)が多かったのですが、だんだん難しくなってきたため、院外処方(=処方箋をもらって処方箋を扱う薬局で薬をもらう形)に代わってきました。しかし薬価がない薬はそのようなことがないため、院内処方であることが多い印象があります。病院経営のためには仕方がないんでしょうかね。そのため、調剤薬局勤務の薬剤師は薬価未収載薬に触れる機会があまりなく、いざ患者さんが来られたら薬をお渡しすることにとまどってしまう、という悪循環になっているのではないでしょうか?
薬価未収載薬特有の問題
薬価未収載薬には避妊薬、勃起不全薬(ED)、脱毛症(AGA)の薬などがあります。どれも病院にかかるのに敷居の高いものだと思います。何か言われないかと不安に思ってネットで個人輸入したりする場合が多いようです。外国のものだとどのような過程で製造されているかよくわかりません。なにか副作用があっても言葉が通じない相手では泣き寝入りする可能性が高いです。通常医薬品できちんと用量用法を守っていたのに副作用が出た場合、副作用救済制度というものがあるのですが、個人輸入でそのようなことがあっても制度を使えません。個人輸入に頼らなくてもよいルールを整えてほしいと思います。
皆さんの意見がありましたら、お問い合わせフォームからよろしくお願いいたします。

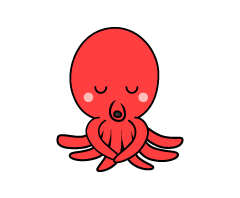
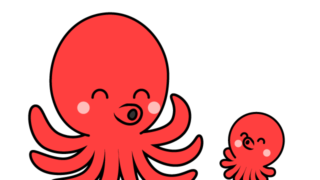
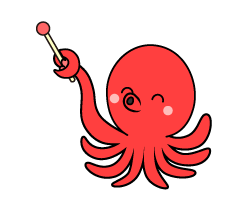








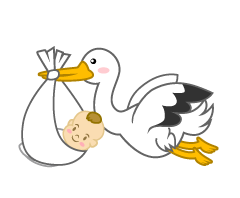


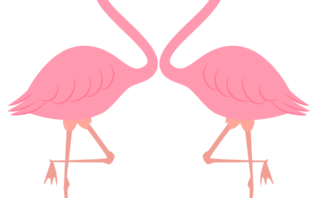
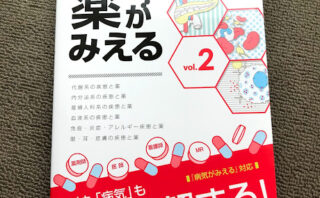






コメント