こんにちは。調剤薬局勤務18年の薬剤師のタコ🐙です。前回に引き続きなぜ薬局によって払う金額が変わるのか?調剤報酬の計算の方法についてお話していきます。今や調剤薬局は病院や開業医の近く、ドラッグストアに併設されているところ、住宅街の中などたくさんありすぎてどこにするかわからない、と思っている方も多いと思いますが、前回では調剤基本料に違いをつけることにより同じように見える調剤薬局も違いがあるということをお話いたしました。
ここからはその他、条件を満たせば技術料(=手数料)として取ることができる点数を加算というのですが、店舗によって設備など違いがあるため料金に違いが生じます。特に重要な加算を中心にお話していきます。

後発医薬品調剤体制加算
- 後発医薬品調剤体制加算1(15点):後発医薬品の調剤数量が75%以上
- 後発医薬品調剤体制加算2(22点):後発医薬品の調剤数量が80%以上
- 後発医薬品調剤体制加算3(28点):後発医薬品の調剤数量が85%以上
- 後発医薬品減算(-2点):後発医薬品の調剤数量が40%以下
現在国が医療費削減のために強く推し進めている政策の1つが後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及です。後発医薬品は皆さんもご存じの通り新しい主成分の新製品(=先発医薬品)が特許切れになった後、他の製薬会社が主成分が同じもので作った製品のことです。主成分の特許は切れていても薬の形にするには錠剤や粉薬(散剤、顆粒剤と呼ばれます)などにするための技術(=製剤)があり、そこに特許が生じている場合、先発医薬品とは混ぜ物を変えざるを得ない場合があります。いろいろな制約の範囲内で効果が同等とされたものを後発医薬品として認められています。後発医薬品は先発医薬品と同じですと説明されると思いますが、効果が同等という意味です。しかし、現在登場している先発医薬品の中には錠剤1錠で、または注射1本で何万円、何十万円もするものがでてきています。ありふれた病気の薬はかなり少なくなり、日本で5万人未満の病気(=希少疾病)に使う薬が多くなっています。このような薬をオーファンドラッグと呼んでいます。オーファンドラッグは開発しても使える対象患者さんが少ないため、完成した場合は薬価が高く設定されます。そのような背景があるため、後発医薬品が存在するような古い薬は薬価を安くしなければならないのです。医療を受ける一人一人が社会保障を維持するために協力できることはお願いしたいと思います。
前置きが長くなりましたが、この加算は調剤薬局が後発医薬品をどれだけ数量を扱っているかで取っている加算です。その薬局が後発医薬品を扱う割合が高くなれば支払額が高くなります。注意点は自分がもらう薬に1つも後発医薬品がなかったとしても調剤できる体制があるということなので、この料金を支払うことになります。現在は一般名処方といって通常は商品名を処方箋に書くのですが、成分名を書いてある処方箋が一般的になってきました。この場合基本的に後発医薬品を選ぶことになります。
後発医薬品は安いだけではなく、飲みやすくしたり工夫をされているものもあります。後々お話していきます。
薬剤服用歴管理指導料
A.3ヶ月以内に再来店:43点
B.それ以外:57点
継続的に調剤薬局でお薬をもらう場合、たいていは3ヶ月以内には次の診察があると思います。その場合前回と違う薬局に行ってしまうとBの高い点数を取られるということを意味しています。初めての薬局であれば、問診票を書くことになると思います。そのため、時間がかかってしまいます。お金も時間もかかることになります。これも国の政策として患者さん一人一人が行く薬局を決めて行きつけの薬局(=「かかりつけ薬局」と呼んでいます)を持つように勧めている証拠なのです。
前回の調剤基本料と今回の後発医薬品体制加算、薬剤服用歴管理指導料2つで合わせて3点が皆さんにとって身近で重要な点であると思いますので、解説いたしました。前回の記事は以下のリンクにあります。
皆さんの意見がありましたら、お問い合わせフォームからよろしくお願いいたします。

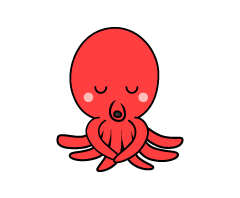
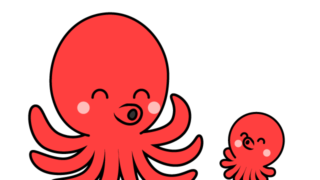
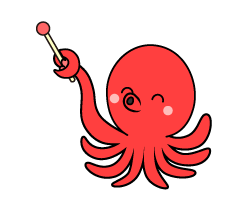


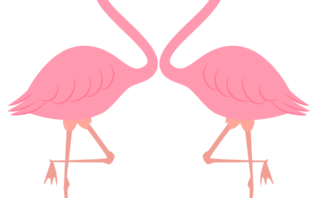



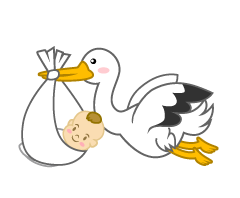

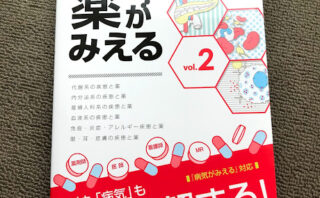








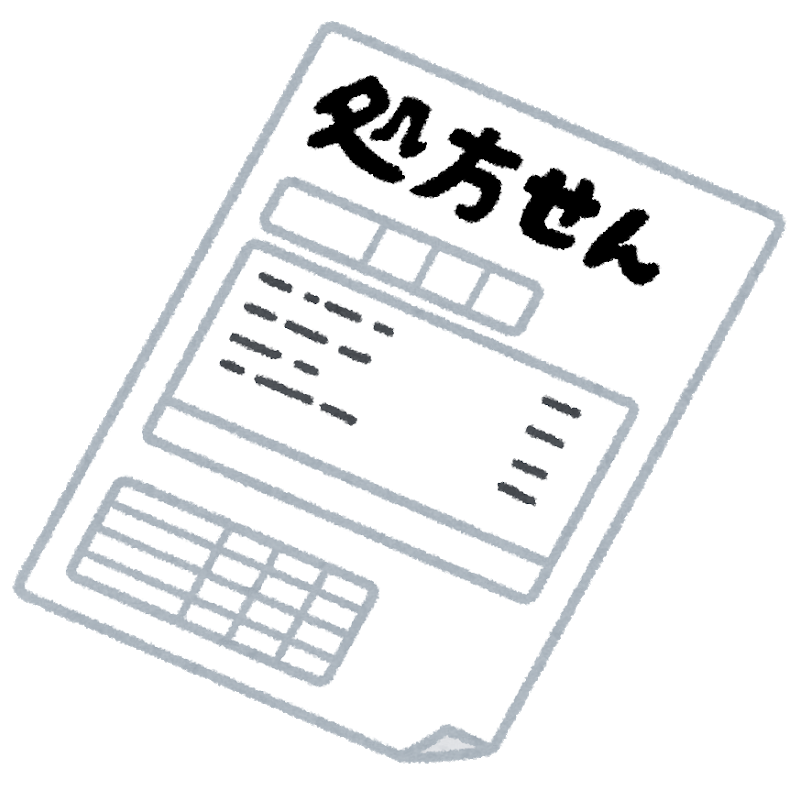



コメント