こんにちは! 薬剤師のタコP🐙です。
この記事を書いた理由
私には他の人にはない特徴があります。それは吃音があるということです。どもりといったりすることもありますが、今は差別用語とされているようです。言い出しの最初の言葉がでないことが特徴です。ただし、いつも起こるわけではなく、特に初めての人に会って話をする時と、電話をする時がよく起こります。もし、この記事を読まれている方で吃音があり、日常生活や職場で支障があったり、悔しい思いをしたことがある方にはぜひ読んでいただき、少しでも力になれればと考えています。
吃音があっても言葉を扱う仕事はできる
吃音があるといわれている有名人はアナウンサーの小倉智昭さんや米国のバイデン大統領などです。言葉を扱う仕事であるにもかかわらず、それを感じさせない仕事ぶりは我々に勇気を与えてくれています。
私の場合
薬局で働く薬剤師の仕事は調剤業務になるのですが、おおまかには基本的に処方箋の内容通りに薬を取り揃え、間違いがないか確認し、薬をお渡しする(=投薬)という流れになります。投薬の際に吃音が出てしまうことがあり、「何言ってるのかわからない」と言われることもあります。
自ら吃音を持つ医師の著書
これから紹介するのは子供のころから吃音があり、それを治療する方法を見つけるために医師を志し、治療する方法はないものの、医師になった現在、吃音の外来をされているようですが、患者さんを呼ぶのが苦手なので、看護師さんに呼んでもらうなど業務を工夫することによって吃音の影響を最小限にしているようです。
本に書かれている中で私も含めて最も参考になると思われる部分があります。それは吃音のある人が共通して困っているであろう日常生活の場面でどのように対応すればよいか「知恵の分かち合い」というものがあったので、ご紹介します。
- 国語の本読みが苦手
⇒例として、本読みを一番に当ててもらったり、最初の部分だけ一緒に行ってもらう。 - 「おはようございます」「ありがとうございました」が言えない
⇒「はようございます」「りがとうございました」「らっしゃいませ」でも相手に通じる。最初の言葉を省略してみる。そして、相手の目を見て笑顔でお辞儀する。 - 駅の切符・映画のチケットが買えない。タクシーで行き先が言えるか不安。クリーニングなど窓口で名前を言えない
⇒用件(名前、行き先)を書いたメモを差し出すことによって、正確に早く伝わる。 - 電話をかけるのが怖い
⇒まず間違い電話ではないことを知ってもらう。「おはようございます」「こんにちは」など言いやすい言葉を最初に言う。
あらかじめ録音した自分の声を電話を掛けるときに再生する。
ファックスで伝えたい内容をあらかじめ送っておいてから電話する。
伝えたい内容を正確に伝えるのがコミュニケーションの一番大事なことである。 - 人前で話すのが怖い
⇒すらすらしゃべろう、吃音を隠そうと思うと、余計なプレッシャーがかかる。
自分の吃音をカミングアウトしてから話し始めると、吃音を隠す努力が不要になる。 - 親しい人に吃音のカミングアウトをしたい
⇒直接話す勇気がないのなら、ブログやホームページ、またはメールを使って告白してもいい(詳細な説明もできるため)。 - 「どもったらどうしよう」という予期不安をなくしたい
⇒「吃音を隠す」という目標をやめて、第一目標を「言いたいことを言う」にする。どもっても安全な場所(セルフヘルプグループ)で言いたいことをしゃべる。 - どもった後の落ち込みを減らす
⇒「どもること=悪い」が引き起こす悪循環をやめればいい。どもって失敗した話を自分の内にしまい込まずに、共感してくれる人に話す。「吃音の悪口を言った人は、心無い人だった」と思えばいい。
ボクは吃音ドクターです。菊池芳和著 P181~183
この「知恵の分かち合い」に書かれていることはすべて私に当てはまることでした。すなわち、吃音を持っている人は同じ悩みを抱えていることになるのです。吃音はおそらく完治することはないけれど、対処法は分かれば気が楽になりました。
大人同士の場合、周りに吃音の人がいれば茶化すことなく、一つの特徴ととらえて見守ってほしいと思います。
ご紹介した本です。興味があれば一度お読みください。

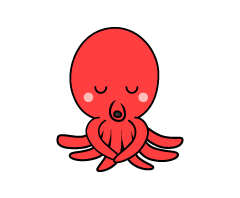
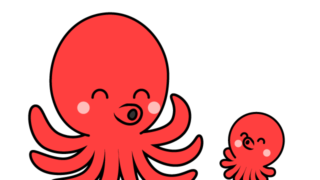
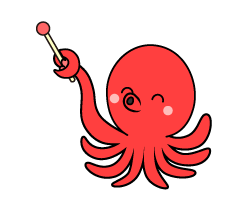



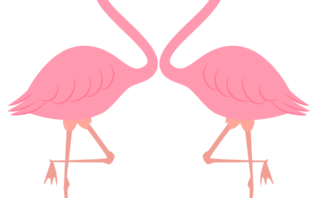


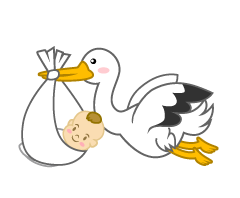





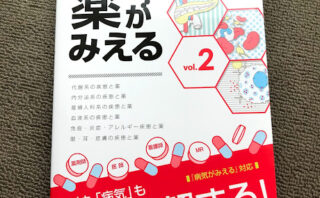





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20e34bbb.f054aba3.20e34bbc.a532ca33/?me_id=1278256&item_id=16527379&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4926%2F2000000164926.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント