こんにちは。薬剤師のタコP🐙です。お薬のお話と40代からの子育てについて書いています。今回の記事は特にこれから将来の進路を決めようとする高校生に読んでいただき、現在将来の進路として6年制薬学部が選択肢にある高校生の方々に将来得られるであろう収入はどれくらいか、今薬剤師の置かれている現状についてまとめました。さらにそれを踏まえて学生の間に何かできることはないか考える機会にしていただければ幸いと思います。
薬学部の定員について
本日厚生労働省の薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会から発表された資料によるとこれからの薬剤師の養成に関する提言で
将来的に薬剤師が過剰になると予想される状況下では、入学定員数の抑制も含め教育の質の向上に資する、適正な定員規模のあり方や仕組みなどを早急に検討し、対応策を実行すべき。
厚生労働省HPより 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ(提言概要)」
これはどういうことなのか?これまでは薬学部を設置する大学が年々増加してきました。この理由として
- 医療系国家資格は就職に強いことが社会的に認知されているため、新設大学でも学生を集めやすい。
- その中でも薬学部は比較的少ない設備でも運営が可能。
- 人口が減っている地方都市では大学を誘致するのが町おこしとしては最適。場合によっては卒業後もそのまま就職してくれるかも?と期待している。
のようなことが考えられます。基本的には大学を設置したいと申請があれば、よほどの問題がなければ認められるようです。しかし、このことは大学全体に言えることかもしれませんが、薬学部の定員が増えすぎた結果、入学試験が簡単になりすぎ、大学の講義についていけない学生が増加しているという結果になっています。そして留年や国家試験に合格するのが難しいと思われる学生は卒業延期という措置がとられることになります。それは余計に授業料を払わなければならないことにもつながります。さらに、入学させても教育するのが難しいという判断なのか、定員割れの状態で運営している学校も増えてきています。
大学に払う学費について
以下の表は2020年の入学定員充足率、その6年前の2014年の入学生が順調に進級し、入学生の人数を100%として卒業率、国家試験合格率と併せて、2年次以降学校に支払う金額を表しています。学校名は伏せています。
文部科学省ホームページより改変、一部補足
公表されている学費のみで6年間で約1200万円以上かかる計算になります。ここに教科書代、実習費、自宅外であれば下宿代がかかってきます。すべて合算すれば2000万円は必要になります。では、費用が足りない場合、奨学金を借りることになりますが、いくつかの方法があります。
奨学金、収入について
国の教育ローンを借りる
薬学部の場合最大450万円まで、金利1.66%(令和3年5月現在)在学中から利息がつく、在学中は利息のみ返済も可
メリット:入学時に多額の現金が必要になった時に役に立つ
デメリット:在学中から利子が付くため、心理的負担が大きい
日本学生支援機構で借りる
薬学部の場合年間168万円まで、貸与終了時に
固定金利の場合:利率0.268%~0.468%
変動金利の場合:利率0.003%~0.203%(令和3年6月現在)
在学中は利息がかからない
メリット:ほぼ授業料をカバーできる、金利が教育ローンと比較すると安い
デメリット:変動金利では金利上昇のリスクあり。
大学独自の奨学金を借りる
大学によって全く異なります
企業による奨学金
入学時に将来の就職を約束することにより一定年数その企業(ほぼ調剤薬局)で勤務すると返済免除してもらえる奨学金
メリット:奨学金返済の心配をしなくてよい
デメリット:将来の可能性が閉ざされる
大学で講義を受けたり、実務実習に行ったりすると自分の興味が入学時より変わって来ることがあります。しかし、先に就職先を決めてしまうとそれに対応することができなくなってしまいます。病院勤務はできなくなると考えてよいでしょう。
例えば教育ローンと学生支援機構で上限まで借りた場合就職時から月に約7万円、15~20年返済することになります。
一方収入は新卒の場合手取りで
ドラッグストアの場合 月に25~30万円
調剤薬局の場合 月に18~24万円
病院の場合 月に15~20万円
とされていますので、病院勤務では手元に残る現金が月10万円未満になる計算です。これが40代まで続くのです!病院勤務の場合は勤続年数により給料UPはあるでしょうが、薬剤師になると大学の学費が回収できる収入が難しい時代になってきています。
学校によっては入学時から大きく定員割れし、かつ国家試験合格率が悪い学校がいくつかあります。学校名は伏せてありますが、ほとんどが首都圏、関西圏以外に位置している大学です。薬学部では学生時代に実務実習といって授業の一環として実際の職場に研修にいきます。地方の大学では実習先が少なく、出身地に帰って実習を受ける場合もあるようです。この実習にかかる費用は学生が大学の学費とは別に支払うことになります。
少子化にも関わらず、大学の数が年々増加しています。地方の大学に行けば合格して入学するのは容易なことと思われますが、これから薬学部に進学しようとする皆さんにはこのような現状を知って欲しいと切に願います。
私が考えるこれから薬剤師になろうとする人が考えておくべきこと
ここからはすでに6年制薬学部の学生さんに向けてになりますが、私が薬学部を卒業した約20年前は薬局であれば就職先は存分にありましたが、これからは薬局の数が減っていく傾向にあると考えられます。そのため、勤めていた薬局がなくなってしまうということもありえます。最近はジェネリック医薬品ばかり使われるようになったため、新薬メーカーのMR人員も減らされ、薬局現場まで情報が来なくなりました。これは経験の浅い薬剤師にとっては勤務しながら勉強できる機会がなくなっていることを意味します。そこで、薬について自分で勉強できる書籍について書いている記事を紹介しますので、ぜひそちらも見て頂ければありがたいです。

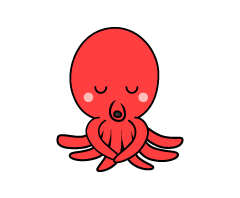
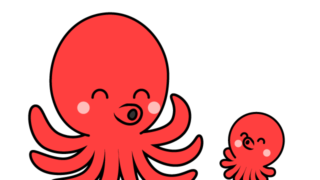
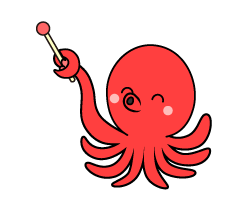


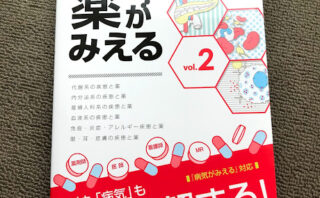



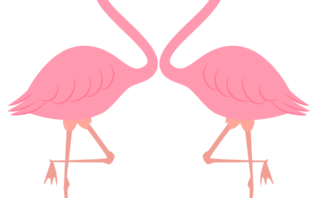







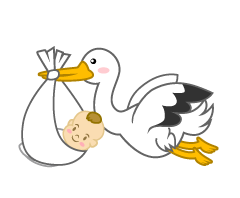



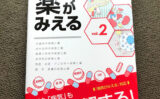

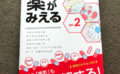
コメント